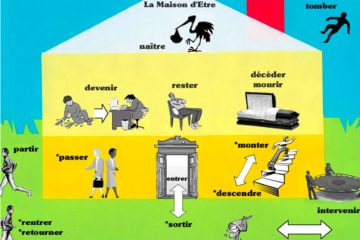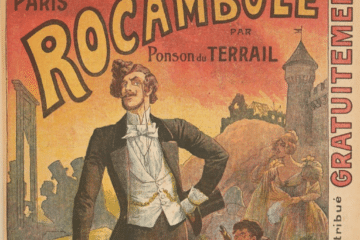“Au hasard des lectures”
こんにちは!フランス語講師のブログへようこそ!!
カルロス・ゴーン被告が昨年の大晦日に日本を脱出しましたね。
今回は年初に出したこの声明文について考えてみたいと思います。なにをしたか?などの行為の是非ではなく、あくまでもフランス語の観点から声明文で使われている la justice とは ?を読み解いていこうと思います。
目次
la justice とは 「私は正義から逃れたわけではない」
私が ゴーン氏の声明文 を目にしたのは昨年12月31日のことでした。ゴーン氏自身が彼の広報担当のフランス企業を通じてこの声明文を発表し、フランス語の原文とその日本語訳が日本経済新聞電子版に掲載されていたのでした。
“Je n’ai pas fui la justice – j’échappe à l’injustice et la persécution politique.”
目を引いたのはこの声明文の一節でした。みなさんならどう訳しますか?特に la justice の意味に注目です!
日本経済新聞では「私は裁判から逃れたのではなく、不公平さと政治的な迫害から解き放たれた。」と翻訳されてました・・・。
ところがです!!
日本経済新聞を除くすべての新聞、そしてゴーン氏の声明文を扱ったテレビ番組では、この”la justice “が例外なく「正義」と訳されていたんです。報道でも「正義」と放送されていたのですがみなさんは見覚え、聞き覚えありませんか?
この la justice とは「正義」なのか?
” La Justice “は直訳では確かに「正義」という意味の単語ですよね。
けれども私は、このケースでは ” la justice ” は「正義」ではなく「司法」と訳するほうが正しく意味を理解できると思います。日本経済新聞では「裁判」と訳されていましたが、これは状況に合わせて「司法」をより具体的に「裁判」として、よりわかりやすくしようとされた訳者の配慮ではないかと思っています。
が、いずれにしても単語のもつ「正義」という意味では声明文の翻訳として合いません。
もう一度見てみましょう。
- 一般報道の翻訳:「私は正義から逃れたのではない」
- 日本経済新聞翻訳:「私は(日本の)司法から逃れたのではない」
としたほうがピンとくると思いませんか?何から逃れたのかが具体的となりしっくりきますね。正義(感)は個人によるものでもありますし訳として曖昧だと思うのです。
La majorité n’a pas toujours raison !
日本経済新聞以外はすべて「正義」と訳しているので完全なマイノリティーなのですが、この件に関してだけは「過半数意見が常に正しいとは限らない!」と主張させていただきたいです!
実際にフランス語原文で彼の声明文を読んだ人たちは、例外なくその意味を「司法」として理解しているのです。
多義語から正しく意味を選ぶには
フランス語が多義語と呼ばれることはこのブログでもお話ししていますが、その多義語を操るフランス人たちは毎日の生活の中で、ひとつの単語から「その状況にふさわしい適切な意味だけを選び取る」という作業に慣れています。
「どうしてそんなことが出来るの?」と思われる方もいらしゃるかも知れません。
けれども例えば、
- la justice を「正義」と訳したとしても、
- le ministre de la justice といえば「正義」の大臣ではなく「法を司る」=法務大臣のこと
と、直訳からよりふさわしい身近な単語に正しく転換できますよね。日本語で理解している・親しみがある・慣れている・単語(訳)であれば、あなたも直訳ではなくより自然な正しい意味を選ぶことができるんです。
なので、原文で彼の声明文を読んだ人たちは、この声明文の状況では la justice をためらくことなく「司法」という意味で理解できたんです。
レトリックという一工夫した言い回し
さらに私はこの声明文の一文を Antanaclaseという修辞法の技法の一つと判断しました。
これはフランス語の多義語性を利用した「レトリック技法」のひとつです。日本語に訳すと『異議複葉法』となって(いっきに10倍くらい難しく聞こえますが)要は1つの文章で同じ単語を2度使って、さらに1度目と2度目では異なる意味で単語を使うというものです。
ゴーン氏の声明文では justice が2度使われているのではなく justice と injustice になっているので、少し変形型なのですが
- 最初の justice は「司法」という意味で
- 2番目は「正義」の反義語の「不正義」「不公正」という意味で
使われています。
ゴーン氏としてはこの「逃亡者のキャッチフレーズ」とも言える、一工夫した言い回しをレトリックを駆使してきっと(結構)一生懸命考えたのでしょうが、当の日本ではその効果もなく伝わらなかったようですね。
なぜ「正義」という訳になったか?
ではなぜ日本のメディアのほとんどが「正義」という訳を選んだのでしょうか?
私はゴーン氏の正式コメントが英語で出されたことに関係があるのではないかと考えています。英語の “justice”にも司法の意味はあると思いますが、先ほどご紹介したレトリックが英語ではあまり効果的ではないんだろうなと考えるのです。
この辺りは英語が得意ではない私には想像の域を出ないので、ぜひ英語が得意な方にご意見を伺いたいです。
きっと役に立つ『意義複葉法』の例
せっかくなので、 Antanaclase の有名な例をひとつご紹介しましょう。それは、パスカルによる次の1文です。
“Le coeur a ses raisons que la raison ne connait point.”
2つのraisonの意味に注目して訳してみましょう。
- avoir ses raisons で「理由がある」
- que は関係代名詞目的格で
- que 以下が先行詞 raison を修飾しています
もうわかりますね。最初のraison は「理由」という意味で、あとのraisonは「理性」という意味で使われています。
直訳すると、
「心には理性が決して知らない理由がある」
つまり、人が愛する理由を理性で説明することはできないと言う意味ですね。
パスカルの文章が少し難しければ、” l’amour a ses raisons que la raison ignore” という散文バージョンも覚えやすいのでおすすめですよ。
いかがでしたか? 日本人から見ればいかにもフランスらしい一文なので、もしご存知なかったのならこの機会にメモってどこかで使ってみては!
また、レトリックは決して覚えなければならないものではありませんが、フランス語の表現の理解に役立つものも多いです。機会があれば、少しづつ分かりやすい例をご紹介していきたいと思います。